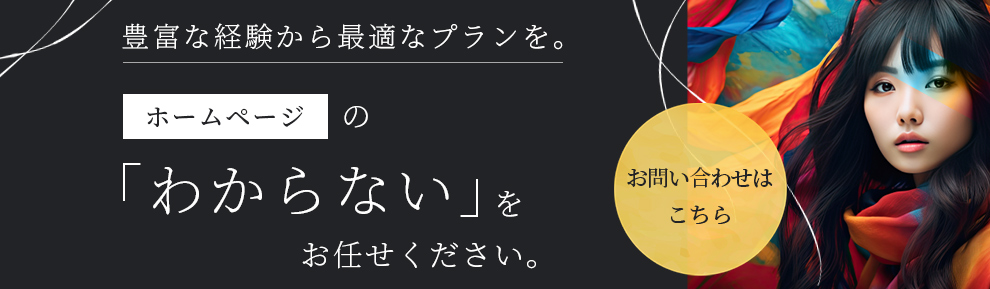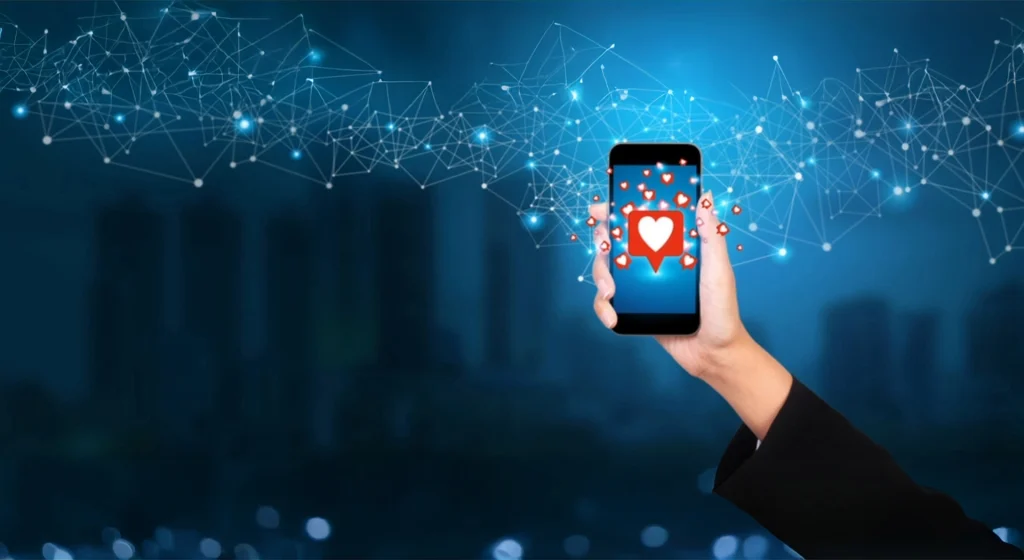-
見分けやすい色 組み合わせ例|Webデザイン、資料作成に役立つ配色テクニック
最終更新日:2025年9月22日

RYO ONJI
株式会社CIZRIA代表
Web黎明期より20年以上業界に携わり企業、フリーランスを経て株式会社CIZRIAを設立。700以上のWebサイト制作に携わったことでSEO対策やWebマーケティングへの知識を深める。
Webサイトや資料のデザインにおいて、色の選択は非常に重要です。しかし、どのような色の組み合わせが「見やすい」のか、多くの方が悩んでいるのではないでしょうか。本記事では、Webデザインや資料作成に役立つ「見分けやすい色の組み合わせ例」を、具体的な事例を交えて解説します。色のコントラストの基本から、カラーユニバーサルデザイン、色覚多様性への配慮まで、デザインの質を格段に向上させるための情報を網羅。さらに、株式会社CIZRIAのWeb制作事例を通して、実践的なテクニックを学びましょう。あなたのデザインスキルをレベルアップさせるための、第一歩を踏み出しましょう。

Contents
見分けやすい色 組み合わせとは?デザインにおける色の重要性
デザインにおいて、色は情報を伝えるための強力なツールです。しかし、その使い方を誤ると、かえって情報を分かりにくくしてしまうこともあります。特に、Webサイトや資料のデザインでは、色の選択がユーザーエクスペリエンスを大きく左右します。本セクションでは、デザインにおける色の重要性を再認識し、その基本となる考え方について解説します。
色のコントラストとは?
色のコントラストとは、2色以上の色の対比のことです。コントラストの強弱は、色の組み合わせによって決まり、デザインの見やすさに大きく影響します。コントラストが弱いと、文字や要素が見分けにくくなり、情報が伝わりにくくなります。逆に、コントラストが強すぎると、目がチカチカしてしまい、長時間の閲覧には適しません。適切なコントラストを設定することが、デザインの視認性を高めるために重要です。
色のコントラストを意識する上で重要なのは、明度差と色相差です。明度差とは、色の明るさの差であり、明度差が大きいほどコントラストは強くなります。色相差とは、色の種類(赤、青、緑など)の違いであり、色相差が大きいほど、それぞれの色は区別しやすくなります。
カラーユニバーサルデザインとは?
カラーユニバーサルデザイン(CUD)とは、色覚に多様性を持つ人々(色覚異常者など)を含む、すべての人々が快適に利用できるように配慮したデザインのことです。具体的には、色覚特性の違いによって色の見え方が異なる人々にも、情報が正確に伝わるように配慮した色の選択や組み合わせを行います。CUDの考え方をデザインに取り入れることで、より多くの人に情報を届けることが可能になります。
CUDの実現には、色の組み合わせだけでなく、色のコントラスト、文字の大きさ、アイコンのデザインなど、様々な要素への配慮が必要です。例えば、赤と緑の組み合わせは、色覚異常を持つ人々には区別がつきにくい場合があります。このような場合、赤の代わりに青や黄色を使用したり、色だけでなく形やパターンで情報を区別できるように工夫することが重要です。
見分けやすい色の組み合わせ例
Webデザインや資料作成において、色の組み合わせはデザインの印象を大きく左右します。ここでは、具体的な事例を交えながら、見分けやすい色の組み合わせについて解説します。色のコントラストを意識し、カラーユニバーサルデザインの考え方を取り入れることで、より多くの人に情報を届けられるデザインを目指しましょう。
Webデザインにおける色の組み合わせ
Webデザインでは、ユーザーが見やすく、情報を理解しやすいように、適切な色の組み合わせを選ぶことが重要です。背景色、文字色、ボタンの色など、様々な要素を考慮して、最適な配色を検討しましょう。
背景色と文字色の組み合わせ
背景色と文字色の組み合わせは、Webサイトの視認性に大きく影響します。最も重要なのは、十分なコントラストを確保することです。背景色が明るい場合は、文字色を濃い色に、背景色が暗い場合は、文字色を明るい色にすることで、コントラストを高く保ち、文字を読みやすくできます。例えば、白背景に黒文字、または黒背景に白文字は、コントラストが高く、視認性に優れています。しかし、強すぎるコントラストは、かえって目が疲れやすくなる場合もあるため、適度なコントラストを意識しましょう。また、背景色と文字色の組み合わせを選ぶ際には、色の組み合わせによる印象も考慮することが重要です。例えば、暖色系の背景色に寒色系の文字色を組み合わせると、落ち着いた印象を与えることができます。
ボタンの色
Webサイトのボタンの色は、ユーザーの行動を促すために重要な要素です。ボタンの色を選ぶ際には、目立つ色を選ぶだけでなく、他の要素とのバランスを考慮することが重要です。一般的に、ボタンには、背景色とは異なる、目立つ色を使用します。例えば、青色の背景には、オレンジ色のボタン、または緑色の背景には、赤色のボタンなどです。ただし、あまりにも多くの色を使用すると、サイト全体の統一感が損なわれる可能性があります。ボタンの色は、サイトのデザインテーマやブランドイメージに合わせて、慎重に選ぶ必要があります。また、ボタンの色を選ぶ際には、色のコントラストだけでなく、ボタンの形状やサイズも考慮することで、より効果的にユーザーの注意を引くことができます。
資料デザインにおける色の組み合わせ
資料デザインにおいても、見やすい色の組み合わせは、情報の伝達効率を大きく左右します。グラフや表、プレゼンテーション資料など、それぞれのデザインに適した色の組み合わせを選ぶことが重要です。
グラフの色使い
グラフは、データを視覚的に表現するためのツールです。グラフの色使いは、データの比較や分析を容易にするために重要です。グラフの色を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- 色の数を絞る: グラフに使用する色は、3~5色程度に絞ることで、見やすさを向上させます。多くの色を使用すると、かえって情報が分かりにくくなる可能性があります。色数を絞ることで、グラフの各要素が区別しやすくなり、データの比較が容易になります。
- 色のコントラストを意識する: グラフの要素間のコントラストを高く保つことで、視認性を高めます。例えば、背景色とグラフの色、またはグラフの要素間の色に、十分なコントラストをつけることで、それぞれの要素が明確に区別できるようになります。
- 色の意味を統一する: 特定の色に特定の意味を持たせることで、データの解釈を容易にします。例えば、成長を表すデータには緑色、減少を表すデータには赤色を使用するなど、色と意味を結びつけることで、データ全体の理解を深めることができます。
プレゼンテーションの色使い
プレゼンテーション資料の色使いは、聴衆の理解度や印象を大きく左右します。プレゼンテーション資料の色を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- 背景色と文字色のコントラスト: プレゼンテーション資料では、背景色と文字色のコントラストが非常に重要です。背景色が明るい場合は、文字色を濃い色に、背景色が暗い場合は、文字色を明るい色にすることで、視認性を高めます。例えば、白背景に黒文字、または黒背景に白文字は、コントラストが高く、視認性に優れています。
- 色の数を絞る: プレゼンテーション資料に使用する色は、3~4色程度に絞ることで、見やすさを向上させます。多くの色を使用すると、かえって情報が分かりにくくなる可能性があります。
- 配色パターンの統一: 資料全体で配色パターンを統一することで、デザインにまとまりを与え、見やすさを向上させます。各スライドで異なる配色を使用すると、聴衆の注意が散漫になる可能性があります。テーマカラーやベースカラーを決め、それに合わせた配色パターンを各スライドで適用することで、資料全体の統一感を高めましょう。
- カラーユニバーサルデザインの考慮: 色覚多様性を持つ人にも配慮した配色を選ぶことで、より多くの人に情報を届けられます。例えば、赤と緑の組み合わせは、色覚異常を持つ人には区別がつきにくい場合があります。この場合、赤の代わりに青や黄色を使用するなど、色の組み合わせを工夫することで、より多くの人に情報を伝えることができます。
色覚多様性への配慮
色覚シミュレーションツール
Webデザインや資料作成を行う上で、色覚多様性への配慮は欠かせません。デザインが色覚特性の異なる人々にも適切に伝わるかを確認するために、色覚シミュレーションツールの活用が有効です。これらのツールを使用することで、作成したデザインが色覚異常を持つ人々にはどのように見えるかを、視覚的に確認できます。
代表的な色覚シミュレーションツールとしては、Adobe PhotoshopやIllustratorに搭載されている機能があります。これらのツールを使用すると、デザインを様々な色覚タイプ(1型2色覚、2型2色覚、3型2色覚など)でシミュレーションし、色の組み合わせがどのように認識されるかを確認できます。また、Webサイト上で利用できる無料のシミュレーションツールも多数存在します。これらのツールは、WebサイトのURLを入力するだけで、そのサイトが色覚多様性を持つ人々にとって見やすいかどうかをチェックできます。具体的なツールとしては、以下のようなものが挙げられます。
- Adobe Photoshop/Illustratorの色覚シミュレーション機能: デザインツール内で完結するため、手軽にシミュレーションできます。
- WebAIM Color Contrast Checker: ウェブアクセシビリティの専門家が提供するツールで、色のコントラスト比をチェックできます。
- Color Oracle: デスクトップアプリケーションとして利用でき、デザイン全体の色覚シミュレーションが可能です。
これらのツールを活用することで、デザイン制作の初期段階から色覚多様性への配慮を取り入れ、より多くの人々に見やすいデザインを作成できます。
色覚多様性への配慮に基づいた色の選び方
色覚多様性を持つ人々への配慮をデザインに取り入れるためには、色の選び方においていくつかの重要なポイントがあります。特に、以下の点に注意することで、より多くの人に情報を伝えやすくなります。
- 色のコントラストを確保する: 背景色と文字色のコントラスト比を高く保つことは、すべての人にとって重要な要素です。色覚異常を持つ人々にとっても、コントラストが高いほど、文字や要素の区別がつきやすくなります。Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) では、コントラスト比の基準が定められており、これに準拠することが推奨されます。
- 色だけでなく、他の要素も活用する: 色だけで情報を伝えるのではなく、形、パターン、テキストの太さ、アイコンなど、他の要素も組み合わせて情報を伝達するようにしましょう。例えば、グラフでは、色だけでなく、線の種類(実線、点線など)やマーカーの形(四角、丸など)を変えることで、色覚異常を持つ人々にもデータを理解しやすくできます。
- 色の組み合わせを工夫する: 色の組み合わせを選ぶ際には、色覚異常者が区別しにくい色の組み合わせを避けることが重要です。例えば、赤と緑の組み合わせは、色覚異常を持つ人々には区別がつきにくい場合があります。このような場合は、赤の代わりに青や黄色を使用するなど、色の組み合わせを工夫しましょう。一般的に、暖色系の色と寒色系の色を組み合わせると、区別がつきやすくなります。
- 色の意味を統一する: 特定の色に特定の意味を持たせることで、情報の理解を促進できます。例えば、警告には黄色、注意にはオレンジ色を使用するなど、色と意味を結びつけることで、より多くの人に情報を伝えやすくなります。
これらのポイントを踏まえ、デザインを作成する際には、色覚シミュレーションツールで確認を行いながら、色覚多様性を持つ人々にも配慮した配色を心がけましょう。

株式会社CIZRIAのWeb制作事例紹介
Webデザインの世界では、理論を知るだけでなく、実際にどのような事例で「見やすい色」が実現されているのかを理解することが重要です。ここでは、株式会社CIZRIAが手掛けたWeb制作事例を通じて、見やすい配色とカラーユニバーサルデザイン(CUD)の具体的な活用方法をご紹介します。
見やすい配色を意識したWebサイト事例
CIZRIAが制作したWebサイトの中には、ユーザーにとって「見やすさ」を最優先に考え、洗練された配色を実現している事例が数多くあります。これらのサイトでは、単に美しいだけでなく、情報が直感的に伝わるように工夫されています。例えば、
- 背景色と文字色のコントラスト: 白を基調とした背景に、濃い青色の文字を組み合わせることで、高いコントラストを実現し、可読性を高めています。また、重要な情報には、背景色と異なる色を使用し、視覚的なアクセントとしています。
- 色の組み合わせ: ブランドイメージに合わせた配色を採用しつつ、ユーザーが見やすいように、色相、彩度、明度のバランスを調整しています。例えば、寒色系の背景画像に暖色系の文字色を組み合わせることで、落ち着いた印象を与えつつ、情報の区別を容易にしています。
- ボタンの色: CTA(Call To Action)ボタンには、背景色と対照的な色を使用し、ユーザーの視線を誘導しています。ボタンの色だけでなく、形状やサイズも考慮し、ユーザーがクリックしやすいように設計されています。
これらの事例から、CIZRIAがWebサイト制作において、色の選択がいかに重要であるかを理解できます。単にデザイン性が高いだけでなく、ユーザーエクスペリエンスを向上させるための配慮がなされています。
まとめ:見やすい色の組み合わせで、より多くの人に情報を届けよう
本記事では、Webデザインや資料作成において、見やすく、情報を伝えやすくするための色の組み合わせについて解説しました。色のコントラストの重要性から、カラーユニバーサルデザイン、色覚多様性への配慮まで、デザインの質を向上させるための具体的なテクニックを紹介しました。
デザインにおいて、色の選択は、ユーザーエクスペリエンスを大きく左右します。今回ご紹介した情報を活用し、デザインのスキルを向上させ、より多くの人に情報を届けられるようにしましょう。株式会社CIZRIAの事例も参考に、ぜひ実践してみてください。
- デザインが古く、ブランドイメージに合っていない
- サイトの使い勝手が悪く、訪問者がすぐに離脱してしまう
- 問い合わせや購入につながる導線ができていない
- SEO対策が不十分で、検索結果で上位表示されない
- ホームページを作ったものの、運用・更新の仕方がわからない
-
ホームページ制作:洗練されたデザインと本質的な機能を融合
-
SEO対策:検索エンジンでの上位表示を狙い、集客力を強化
-
運用サポート:更新や改善のアドバイスで、長期的な成果を実現
ビジネスの可能性を広げるホームページを、CIZRIAが全力でサポートします
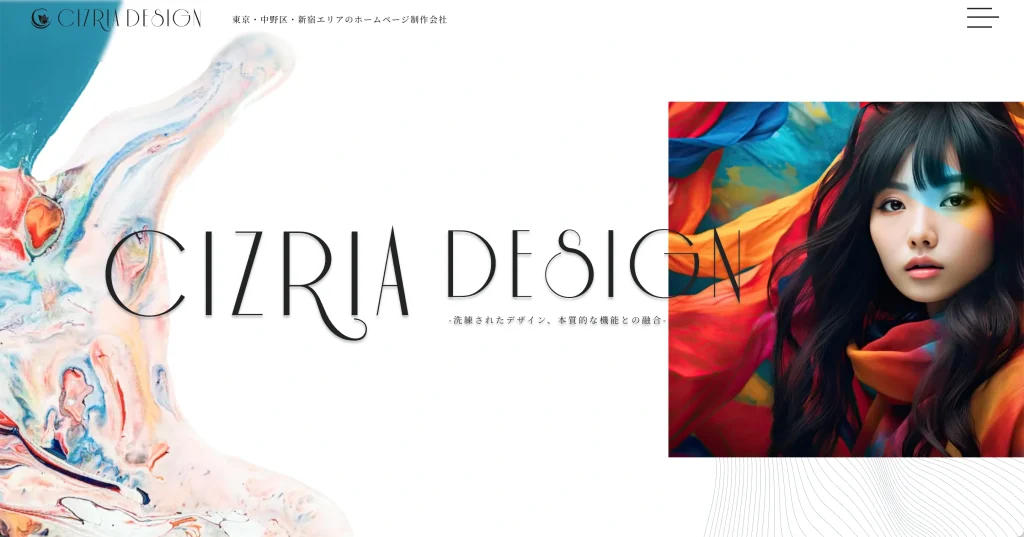
ホームページは、企業の顔であり、ビジネスを成長させる重要なツールです。
「デザインが洗練されていること」「使いやすさを追求していること」「成果につながること」
このすべてを叶えるホームページを、CIZRIAがご提案します。
課題を抱えていませんか?
CIZRIAは、これらの課題を解決し、貴社のビジネスを次のステージへ導きます。
株式会社CIZRIAの強み
お客様の課題はさまざまですが、まずはしっかりと耳を傾け、想いを重ねることを最も大切にしています。
日々進化するホームページ制作の手法やSEO対策の知識、問い合わせや購入へと導く導線設計、視覚的に魅力を引き出すデザインなど、すべてお任せください。
CIZRIAのスタッフは、常に学び、寄り添う姿勢を大切にしながら、貴社にとって最適なご提案をいたします。
「貴社のビジネスの先にある笑顔のために」—私たちが全力でサポートします。
株式会社CIZRIAのサービス
ホームページは作って終わりではなく、成長し続けるものです。
CIZRIAは、貴社のビジネスを加速させるパートナーとして、継続的にサポートいたします。
貴社の理想のホームページを、CIZRIAとともに実現しませんか?
-

グーグルマップの使い方を徹底解説!初心者でも迷わない基本操作から応用まで
初めての場所へのお出かけや、旅行先での道案内、もう迷うことはありません!この記事では、グーグルマップの使い方を初心者向けに徹底解説します。基本操作から、場所検索、ルート検索…
-

インスタ画像保存の裏ワザ!安全な方法から注意点まで徹底解説
RYO ONJI 株式会社CIZRIA代表 Web黎明期より20年以上業界に携わり企業、フリーランスを経て株式会社CIZRIAを設立。700以上…
-

ホームページ・リニューアルの見極め
WEBサイトをリニューアルするタイミングは会社によって様々ですが、一体どんな理由で改修に踏み切っているのでしょうか。 下記に一般的なリニューアル要件としての項…