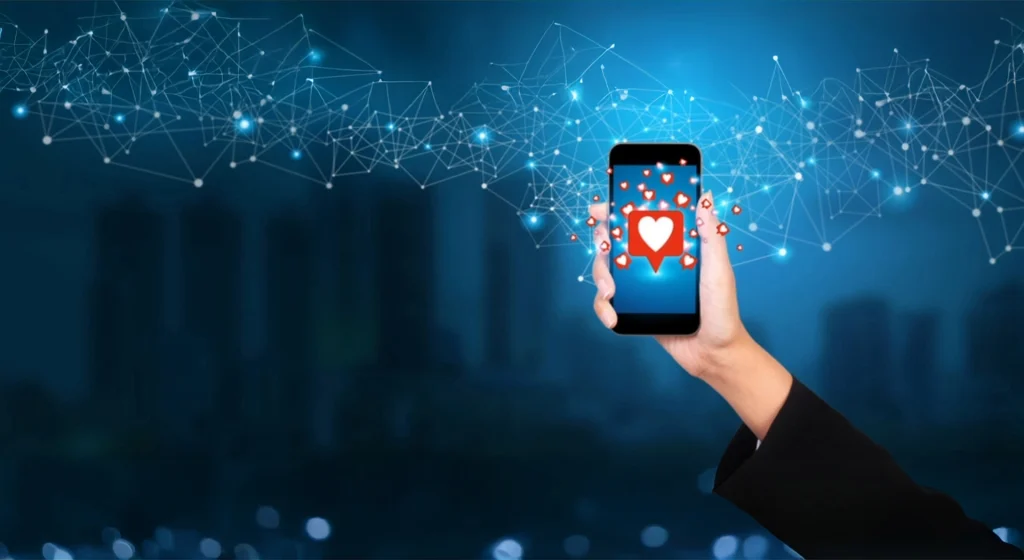-
新米ウェブ担当者向け!ホームページ制作費の勘定科目入門
最終更新日:2025年8月12日
ホームページ制作にかかる費用を適切に処理するために、勘定科目の知識は必須です!
この記事では、ホームページ制作会社目線で、新米ウェブ担当者さんにも分かりやすく勘定科目の説明をします。
専門用語はできるだけ避け、会計処理のプロセスを丁寧に解説しますので、安心して読み進めてください。

RYO ONJI
株式会社CIZRIA代表
Web黎明期より20年以上業界に携わり企業、フリーランスを経て株式会社CIZRIAを設立。700以上のWebサイト制作に携わったことでSEO対策やWebマーケティングへの知識を深める。
Contents
ホームページ制作費の勘定科目:基本編
ホームページ制作費用を適切に計上するために、まず知っておきたいのが勘定科目です。
一口にホームページ制作費用といっても、その計上方法はケースによって異なります。
大きく分けて「広告宣伝費」と「無形固定資産」の2つの勘定科目が使われますが、どちらを使うべきか迷う方も多いのではないでしょうか?
この章では、それぞれの勘定科目の使い分けを具体例とともに分かりやすく解説します。
広告宣伝費を使うケース
ホームページ制作費用を「広告宣伝費」で処理するケースは、ホームページが主に集客や宣伝を目的としている場合です。
例えば、商品の販売促進やサービスの告知を目的として制作されたホームページなどは、広告宣伝活動の一環として捉えることができるため、広告宣伝費に計上するのが一般的です。
具体例としては、短期的なキャンペーンサイトや、特定の商品の販売促進を目的としたランディングページなどが挙げられます。
これらのホームページは、比較的短い期間で役割を終えることが多く、長期間にわたって資産として保有されるものではないため、広告宣伝費として費用処理するのが適切です。
無形固定資産を使うケース
一方、「無形固定資産」で処理するケースは、ホームページが会社の事業活動に永続的に貢献すると考えられる場合です。
例えば、企業の顔となるコーポレートサイトや、長期間にわたって顧客との接点を維持するためのECサイトなどは、無形固定資産として計上するのが一般的です。
無形固定資産として計上した場合、その費用は一度に費用として処理されず、耐用年数に応じて減価償却が行われます。
つまり、ホームページの費用を数年間にわたって少しずつ費用計上していくということです。
これは、ホームページが長期間にわたって事業に貢献するため、その費用を適切に配分する必要があるためです。
その他の勘定科目
上記以外にも、ホームページ制作に関わる費用を計上する勘定科目は存在します。
例えば、ホームページ制作に関連する人件費は「給料」、「旅費交通費」といった勘定科目で処理されます。
また、外部のデザイナーやライターに支払う費用は、「外注費」として計上するのが一般的です。
それぞれの費用を適切な勘定科目に振り分けることで、正確な会計処理を行うことができます。
もし、どの勘定科目を使えば良いか迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
ホームページ制作に関わるその他の費用と勘定科目
ホームページ制作には、制作費以外にも様々な費用が発生します。
それらを正しく会計処理するためには、それぞれの費用に適切な勘定科目を選択することが重要です。
ここでは、代表的な費用と、それぞれの勘定科目について解説します。
サーバー費用
ウェブサイトを公開するために必要なサーバーの利用料金は、「通信費」または「サーバー使用料」などの勘定科目で処理するのが一般的です。
月額料金の場合は、毎月の発生時に計上します。
年間契約の場合は、契約時に費用を計上するか、毎月の償却として計上するか、どちらの方法でも問題ありません。
重要なのは、会計処理の方法を統一し、正確に記録することです。
ドメイン費用
ドメイン名取得費用は、「ドメイン取得費」という勘定科目を使うか、または「通信費」に含めて処理することもできます。
これもサーバー費用と同様に、契約期間に応じて計上方法を検討しましょう。
年間契約で一括で支払った場合は、その年の費用として計上するか、もしくは数年間にわたって償却していく方法があります。
保守・メンテナンス費用
ホームページの保守・メンテナンス費用は、「修繕費」や「雑費」で処理されることが多いです。
定期的なメンテナンス契約の場合、毎月の料金を計上します。
不定期なメンテナンス費用が発生した場合は、その都度計上しましょう。
費用が発生した際に、必ず領収書や請求書を保管しておくことを忘れないようにしましょう。
デザイン費用
ホームページのデザイン費用は、ホームページ制作費と同様に、「広告宣伝費」または「無形固定資産」に計上します。
ホームページのデザインが、長期間にわたって事業に貢献するものであると判断できる場合は「無形固定資産」として計上し、償却していくことが適切です。
一方、短期的なキャンペーンサイトなどであれば「広告宣伝費」として計上するのが一般的です。
ライティング費用
ホームページに掲載する文章を作成するためのライティング費用は、「広告宣伝費」または「原稿料」で処理します。
これも、制作した文章が長期的に利用されるものであれば「無形固定資産」として扱うことも考えられますが、多くの場合は「広告宣伝費」として計上するのが一般的です。
費用を計上する際は、必ず業務内容と費用を明確に記載した請求書を保管しましょう。
これらの費用を正確に計上するためには、それぞれの費用の性質を理解し、適切な勘定科目を選択することが大切です。

正確な会計処理のためのポイントと注意点
ホームページ制作にかかる費用を正確に計上するためには、いくつかのポイントと注意点を理解しておく必要があります。
適切な会計処理を行うことで、税務調査への対応もスムーズになり、事業の健全な運営に繋がります。
ここでは、特に重要な点を3つの項目に分けて解説します。
領収書・請求書の管理
ホームページ制作費用に限らず、あらゆる経費の会計処理において、領収書や請求書の適切な管理は不可欠です。
紛失や破損を防ぐため、整理された状態で保管することが重要です。
具体的には、日付、金額、内容、取引先などが明確に記載されているか確認し、ファイリングシステムを活用したり、専用の会計ソフトで管理したりするのも有効です。
領収書は、経費精算の根拠となる重要な書類です。
大切に保管し、万が一紛失した場合には、取引先に再発行を依頼するなど、迅速な対応を心がけましょう。
デジタル化も有効な手段です。
スキャナーで領収書をデジタル化し、クラウド上に保存することで、紛失リスクを軽減できます。
経費精算の手順
経費精算は、会社の規定に従って行う必要があります。
多くの企業では、申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して提出する流れとなっています。
申請書には、日付、金額、内容、担当者名などを正確に記入し、領収書と内容が一致していることを確認しましょう。
経費精算のタイミングも重要です。
月末締め、翌月払いといった企業独自のルールに従い、期日までに手続きを完了させましょう。
もし、手順が不明な場合は、経理担当者などに確認することをお勧めします。
不明点を放置せず、積極的に質問することで、ミスを減らし、スムーズな精算を実現できます。
税務署への報告
ホームページ制作費用を含む全ての経費は、確定申告や税務署への報告に反映されます。
正確な会計処理を行うことで、税務署への報告もスムーズに行うことができます。
税務調査に備え、領収書や請求書などの会計資料は適切に保管しておきましょう。
税務申告には期限がありますので、期日までに必要な書類を揃えて提出することが重要です。
会計ソフトの活用と専門家への相談
ホームページ制作にかかる費用をスムーズに管理するには、会計ソフトの活用が欠かせません。
手作業での会計処理はミスも発生しやすく、時間もかかります。
会計ソフトを使えば、自動で仕訳が行われたり、様々なレポート作成が簡単にできるため、業務効率の大幅な改善が期待できます。
おすすめの会計ソフト
現在、様々な会計ソフトが提供されています。それぞれ機能や価格帯が異なるため、自社の規模やニーズに合ったものを選ぶことが重要です。
いくつか例を挙げ、それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。
- freee(フリー)
- 中小企業向けのクラウド型会計ソフトとして人気が高く、直感的な操作性と充実した機能が魅力です。初期費用が無料で、月額料金も比較的リーズナブルです。
- 弥生会計
- 長年多くの中小企業で利用されてきた実績のある会計ソフトです。機能が豊富で、複雑な会計処理にも対応できます。クラウド版とデスクトップ版が用意されています。
- マネーフォワード クラウド会計
- 請求書発行機能や銀行口座との連携機能など、経理業務を効率化する機能が充実しています。複数のユーザーで同時に利用できるため、チームでの作業にも適しています。
上記以外にも多くの会計ソフトが存在しますので、無料トライアルなどを利用して、実際に操作してみることをおすすめします。
機能だけでなく、サポート体制の充実度も確認しておきましょう。
税理士への相談
会計ソフトの活用に加え、専門家である税理士への相談も非常に有効です。
特に、複雑な会計処理や税務申告など、自身で対応するのが難しい場合は、税理士に依頼することで、正確な処理と節税効果の両方を期待できます。
税理士選びは慎重に行い、信頼できるパートナーを見つけることが大切です。 複数の税理士事務所に相談し、比較検討することをおすすめします。
会計ソフトの活用と税理士への相談を組み合わせることで、ホームページ制作費用を含む会社の会計処理をより正確かつ効率的に行うことができるでしょう。
これは、企業の健全な経営を維持するために不可欠な要素です。
初期費用やランニングコストを考慮した上で、最適な方法を選択し、安心して事業に集中できる環境を構築しましょう。
ホームページ制作費用管理ステップ:実践編
ここまでホームページ制作にかかる費用の勘定科目と会計処理について解説してきました。
理解を深めていただけたでしょうか?
それでは、いよいよ実践です!
この記事で学んだ知識を活かして、自社のホームページ制作費用を効果的に管理するためのステップを3つの段階に分けてご紹介します。
予算策定
ホームページ制作を始める前に、まず予算をしっかりと策定することが重要です。
予算がないと、後々費用が膨れ上がり、計画通りに進められない可能性があります。
予算策定においては、以下の点を考慮しましょう。
- 制作費用の見積もり
- デザイン、開発、コンテンツ作成など、それぞれの費用を正確に見積もります。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することも有効です。
- ランニングコスト
- サーバー費用、ドメイン費用、保守・メンテナンス費用など、制作後にかかる費用も忘れずに算出し、予算に含めます。月額費用や年間費用を明確にしましょう。
- 緊急時の費用
- 予期せぬトラブルが発生した場合に備え、予備費を確保しておくことをおすすめします。想定外の修正や追加作業が発生する可能性も考慮しましょう。
- 目標設定
- ホームページ制作によって達成したい目標(例:売上向上、顧客獲得など)を明確にし、その目標達成に必要な費用を算出します。費用対効果を常に意識することが大切です。
費用の見積もりと管理
予算策定後、実際にホームページ制作を進めていく段階では、費用の見積もりと管理を徹底しましょう。
予算をオーバーしないよう、常に費用を把握することが重要です。
- 詳細な見積書の作成
- 制作会社から見積もりを受け取る際には、項目ごとに費用が明確に記載されているか確認しましょう。不明な点は必ず質問し、納得してから契約しましょう。
- 定期的な進捗報告:
- 制作会社と定期的に連絡を取り合い、進捗状況と費用の状況を確認します。問題があれば早期に解決することで、追加費用が発生するのを防ぎます。
- 支出記録:
- 全ての費用について、領収書や請求書をきちんと保管し、会計ソフトなどを使って記録しましょう。これにより、費用の状況を常に把握し、予算管理をスムーズに行うことができます。
- 予算と実績の比較:
- 定期的に予算と実績を比較し、差異があればその原因を分析します。予算オーバーを防ぎ、今後の費用管理に役立てましょう。
精算と報告
ホームページ制作が完了したら、最終的な精算を行い、関係者へ報告を行います。
正確な会計処理を行うことで、税務上の問題を防ぐことができます。
- 請求書の確認:
- 最終請求書に記載されている金額が、見積もりと一致しているか確認します。誤りがあれば、速やかに修正を依頼しましょう。
- 支払処理:
- 正確な会計処理を行い、適切な勘定科目を選択して費用を計上します。領収書や請求書を大切に保管しましょう。
- 報告書の作成:
- ホームページ制作にかかった費用をまとめた報告書を作成し、関係者(上司や経営者など)に提出します。制作期間、費用内訳、成果などを明確に記載しましょう。
- 税務申告への対応:
- 税務申告に必要な書類を準備し、税理士などの専門家に相談しながら適切な申告を行いましょう。
これらのステップを踏むことで、ホームページ制作費用を効果的に管理し、スムーズな会計処理を実現できます。
費用管理は、ホームページ制作成功の重要な要素の一つです。
しっかりと管理を行い、制作後の運用にも繋げましょう。
よくある質問
ホームページ制作にかかる費用に関する会計処理について、よくある質問をまとめました。
会計処理に迷った際は、ぜひご参照ください。
広告宣伝費と無形固定資産、どちらを使えばいいの?
ホームページ制作費の勘定科目は、ホームページの目的と耐用年数によって異なります。
主に「広告宣伝費」と「無形固定資産」の2つが考えられます。
広告宣伝費は、短期的な効果を目的としたホームページ制作費用に計上します。例えば、期間限定のキャンペーンサイトや、特定の商品・サービスの販売促進を目的としたサイトなどは、広告宣伝費に計上するのが一般的です。一方、無形固定資産は、長期間にわたって使用し、事業に貢献するホームページ制作費用に計上します。会社の顔となるコーポレートサイトや、長期間にわたって顧客との接点を維持するためのECサイトなどは、無形固定資産として計上するのが適切でしょう。
どちらを選択するかは、ホームページの目的や利用期間をしっかりと見極めることが重要です。迷った場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
ホームページ制作費の耐用年数は?
ホームページ制作費の耐用年数は、法令で明確に定められていません。
そのため、会社の状況やホームページの性質などを考慮し、適切な耐用年数を設定する必要があります。
一般的には、3年から5年とされることが多いですが、頻繁に更新が必要なサイトであれば、耐用年数を短く設定することも考えられます。
耐用年数の設定は、減価償却費の計算に影響するため、正確な設定が重要です。
適切な耐用年数について判断に迷う場合は、税理士などの専門家にご相談ください。
領収書をなくしてしまったらどうすればいいの?
領収書をなくしてしまうと、会計処理に支障をきたす可能性があります。
まずは、制作会社に領収書の再発行を依頼してみましょう。
再発行が難しい場合は、銀行の取引明細書やクレジットカードの利用明細書などを証拠として保管し、可能な限り詳細な記録を残しておくことが大切です。
これらの資料を元に、税理士などの専門家に相談し、適切な処理方法を検討しましょう。
税務調査の際に問題となる可能性もあるため、早めの対応が重要です。
日頃から領収書を整理整頓し、紛失しないよう注意しましょう。
新宿ホームページ制作CIZRIAは、経験豊富なスタッフがお客様のホームページ制作を全面的にサポートします。
費用やデザインなど、どんなご要望にも柔軟に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください! - freee(フリー)
- デザインが古く、ブランドイメージに合っていない
- サイトの使い勝手が悪く、訪問者がすぐに離脱してしまう
- 問い合わせや購入につながる導線ができていない
- SEO対策が不十分で、検索結果で上位表示されない
- ホームページを作ったものの、運用・更新の仕方がわからない
-
ホームページ制作:洗練されたデザインと本質的な機能を融合
-
SEO対策:検索エンジンでの上位表示を狙い、集客力を強化
-
運用サポート:更新や改善のアドバイスで、長期的な成果を実現
ビジネスの可能性を広げるホームページを、CIZRIAが全力でサポートします
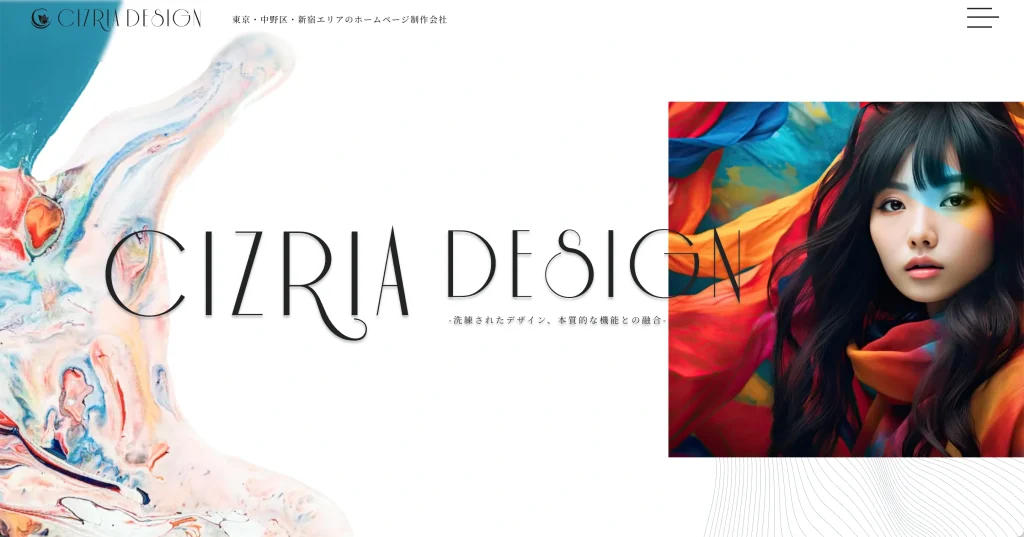
ホームページは、企業の顔であり、ビジネスを成長させる重要なツールです。
「デザインが洗練されていること」「使いやすさを追求していること」「成果につながること」
このすべてを叶えるホームページを、CIZRIAがご提案します。
課題を抱えていませんか?
CIZRIAは、これらの課題を解決し、貴社のビジネスを次のステージへ導きます。
株式会社CIZRIAの強み
お客様の課題はさまざまですが、まずはしっかりと耳を傾け、想いを重ねることを最も大切にしています。
日々進化するホームページ制作の手法やSEO対策の知識、問い合わせや購入へと導く導線設計、視覚的に魅力を引き出すデザインなど、すべてお任せください。
CIZRIAのスタッフは、常に学び、寄り添う姿勢を大切にしながら、貴社にとって最適なご提案をいたします。
「貴社のビジネスの先にある笑顔のために」—私たちが全力でサポートします。
株式会社CIZRIAのサービス
ホームページは作って終わりではなく、成長し続けるものです。
CIZRIAは、貴社のビジネスを加速させるパートナーとして、継続的にサポートいたします。
貴社の理想のホームページを、CIZRIAとともに実現しませんか?
-

グーグルマップの使い方を徹底解説!初心者でも迷わない基本操作から応用まで
初めての場所へのお出かけや、旅行先での道案内、もう迷うことはありません!この記事では、グーグルマップの使い方を初心者向けに徹底解説します。基本操作から、場所検索、ルート検索…
-

ホームページ・リニューアルの見極め
WEBサイトをリニューアルするタイミングは会社によって様々ですが、一体どんな理由で改修に踏み切っているのでしょうか。 下記に一般的なリニューアル要件としての項…
-

インスタ画像保存の裏ワザ!安全な方法から注意点まで徹底解説
RYO ONJI 株式会社CIZRIA代表 Web黎明期より20年以上業界に携わり企業、フリーランスを経て株式会社CIZRIAを設立。700以上…